PR 本ページにはプロモーションが含まれています。
リネンと聞くと「アイリッシュ産」や「リトアニア産」が最高品質、と信じていませんか?
実はその“産地表記”には大きな誤解が潜んでいます。
リネンはヨーロッパで育てられたものだけが特別なのではなく、どこの土地で育ったかよりも、どんな工程を経て仕上げられたかが品質を左右します。
今回は「産地表記はどう決まるのか?」という視点から、アイリッシュやリトアニアという言葉の本当の意味をひも解きます。
リネンの産地表記の真実
リネンの産地表記には国際基準などの明確な基準はなく、メーカーの意向次第で「○○産リネン」と表記されています。
一般的に「リネン」といえばアイリッシュリネン、フレンチリネン、リトアニアリネン、ベルギーリネンと表記されている場合がほとんどで、中には日本製とうたっている国産リネンも存在します。
・原料のフラックスの産地を表記する
・紡績された糸を製織工場の所在地で表記される
これらを基準としている場合が多く、これが混乱の原因となっています。
上にあげた2つの視点の間に重要な工程「紡績」がありますが、紡績工場の所在地が表記されることはほぼありません。
それらの事柄も含めて、リネンの産地表記の真実について深堀をしていきます。
リネン生地ができるまで
リネンは
①【原材料】リネンの原材料となるフラックス(亜麻)の採集
②【紡績】このフラックスを加工して糸にする作業
③【製織】糸を織って布にする作業
この3つの工程を経て出来上がります。
2021年時点で 繊維用途を想定したフラックス繊維(世界のフラックス繊維+短繊維含む)の生産量 は 896,636 トン(およそ 90 万トン弱)だったとの記録があります。
「フラックス」の生産の80%を賄っているのがフランスです。隣接するベルギーとオランダの生産量を合わせると90%以上になります。
フランスのノルマンディー地方やベルギーのフランドル地方は良質なリネン栽培に適した気候と土壌を持つ地域として知られています。
この地域以外で産出される残り10%のフラックスは質の面で劣るものが多いです。アイルランド産、リトアニア産のフラックスもありましたが品質が安定しないため、フランス産を使っています。
これらの事からリネンの原料フラックスはフランス産と言っても過言ではありません。

この事に一番驚きました。なぜなら、リトアニアリネンはリトアニアで育てたフラックスで作られる、と信じていたからです。
原産地はフランスだという事がわかりましたが、この後生産されたフラックスが向かう先は中国の紡績工場です。←ここに注目!!!
ヨーロッパにもフランス・ベルギー・イタリア・ポーランド・ハンガリー・リトアニアにも紡績工場はありますが全体の80%が中国で紡績されます。
中国で紡績された繊維は、もちろん中国でも製織されますが、フランス・ベルギー・イタリア・ポーランド・ハンガリー・リトアニアなどは繊維を中国から輸入し国内の織機で製織しています。
このように、原料生産・紡績・製織がそれぞれ異なる場所で行われています。つまり、産地表記を明確にすることができないため、各メーカーが自由に表記しているという事態になり様々な誤解を生む原因となっています。

以前ご一緒したショップオーナーが「リトアニア産リネンだけを扱っています。リトアニア産こそ最高品質です」と誇らしげに話されていました。
ただ、果たして本当に“産地の名前だけ”で品質が決まるのだろうか?と感じたことがあります。
例えばフランス産のフラックスを中国で糸にして、日本の織機で織ったらそれは「国産リネン」と表記するメーカーもあります。
また、同じようにフランス産のフラックスを中国で糸にして、日本の織機で織っても「アイリッシュリネン」と呼ぶメーカーもあるのです。メーカーの意向次第ですよね。
このように、リトアニアだからいい!とか中国産だから劣る…などと、リネンの良しあしが「生産国や表記」などでは評価できないのです。
リネン生地が高い理由
以上のように、リネンの原材料であるフラックスの80%がフランス産である事、紡績の80%を担っているのが中国の紡績工場である事がわかりました。有名どころの生地の殆どがフランスと中国で生産加工されているのです。
そうなると、価格設定はどうなっているのでしょう?
例えば、ある有名サイトでは「ベルギーリネン」と銘打っているリネンが50cmで1800円、1mだと3600円もの高額になります。実際にベルギーで生産されたわけではないのに、です。
ではなぜ、リネン生地が高いのかについてまとめます。
- 原料(フラックス)の生産が限られている
フラックス(亜麻)は、世界の繊維作物の中でごくわずかしか作られていません。
主な産地はフランス・ベルギー・オランダなど北ヨーロッパで、気候条件も限定されるため大量生産が難しい。コットンやポリエステルと比べて供給量が少なく、希少性が高い。 - 栽培から収穫まで手間がかかる
フラックスは化学肥料や農薬に弱く、繊細な栽培管理が必要。
茎ごと引き抜いて収穫するため、機械化が難しく、人手や特殊な技術が欠かせない。
- 繊維を取り出す加工工程が複雑
リネン繊維を取り出すためには「水に浸す→発酵→乾燥→叩く→しごく」など多段階の作業(レッティング・スカッチングなど)が必要。
工程ごとに技術や設備が求められ、不良率も高い。
- 長繊維ゆえの紡績難度
リネンは繊維が硬くて長いため、糸にするのが難しい。
紡績には専用の機械や熟練の技術が必要で、コストが高くなる。
📍原料のフラックス自体には繊維の長いもの、短いものの違いがあります。その違いで出来上がった繊維や生地がランク付けされていきます。 - 織布と仕上げの工程にもコストがかかる
繊維の硬さゆえに織機への負担が大きく、速度を落として織る必要がある
シワになりやすいため、仕上げ加工(洗い・柔らかくする処理)に手間がかかる。 - 天然素材としての付加価値
吸水性・速乾性・通気性など、夏に最適な素材として高評価。
環境負荷が少ないサステナブル素材という点も価格に反映。
「ヨーロッパリネン」「リトアニアリネン」などブランド価値が付加されやすい。
📍まとめると
リネンは「希少な原料」+「手間のかかる工程」+「高度な技術」が揃って初めて生地になるため、どうしても価格が高くなります。
また、メーカーによっては生機(きばた/何も加工していない状態)で仕入れて、染色したり洗いをかけるなどの加工をして販売しています。手をかけることで価格が上がるのは当たり前の事ではあります。
まとめ
リネンと聞くと「アイリッシュリネン」「リトアニアリネン」といった名前が高品質の代名詞のように語られることがあります。しかし、実際には産地のネームバリューだけで品質が決まるわけではありません。
リネン生地の価格が高いのは、フラックスの栽培から繊維の加工、織布までに多くの手間と技術がかかるからです。限られた産地でしか育たず、加工工程も複雑で、どうしても希少性とコストが上乗せされます。
一方で「中国産」と書かれることを避ける風潮があります。これは消費者のイメージやマーケティング上の戦略によるもので、品質が劣るからではありません。むしろ工場の技術次第で高品質なリネンを生み出すことができます。
つまり、リネンの価値は「産地の名前」ではなく、「どう作られ、どう届けられているか」にあるのです。
YOUTUBEチャンネル「ステラ洋裁店」チャンネル登録お願いします!



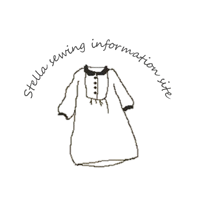



コメント